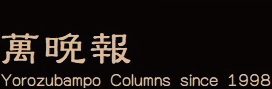人はなぜ戦争をするのか
2025年6月29日、われわれは東かがわ市の大本香川分苑において、世界連邦運動協会四国ブロック協議会を開催した。NPO法人大本イスラエル・パレスチナ平和研究所主任研究員の矢野裕巳氏が「2001年9月11日、ニューヨークでの体験」と題して基調講演した。
興味深かったのは、アインシュタインは、ナチス政権誕生前夜の1932年、国際連盟から「今の文明でもっとも大切な問題について、好きな相手と意見を交換してほしい」という依頼を受けたという話だった。アインシュタインはオーストリアのフロイトを相手に選んだ。人の心理が戦争の大きな背景であることを理解していたアインシュタインは心理学者としてのフロイトの意見に興味を持っていた。1933年、ナチス政権誕生、二人はともにユダヤ系でそれぞれ、アメリカ、イギリスに亡命した。二人の往復書簡が後に「ひとはなぜ戦争をするのか」と題して書籍化された。テーマは「人間の戦争からの解放」。「なぜ少数の人達が多くの国民を動かし、自分達の欲望の道具にすることができるのか」「教養のない人よりも知識人のほうが暗示にかかりやすい」等の問題提起は、現代社会に通じる。フロイトの回答は概ね悲観的だが、「文化の発展を促せば、戦争の終焉へ向けて歩みだすことができる」との一文が一縷の望み。
ひとはなぜ戦争をするのか (講談社学術文庫)
アルバート・アインシュタイン; ジグムント・フロイト; 養老孟司; 斎藤環.
一九三二年七月三〇日
ポツダム近郊、カプートにて フロイト様
あなたに手紙を差し上げ、私の選んだ大切な問題について議論できるのを、たいへん嬉しく思います。国際連盟の国際知的協力機関から提案があり、誰でも好きな方を選び、いまの文明でもっとも大切と思える問いについて意見を交換できることになりました。このようなまたとない機会に恵まれ、嬉しいかぎりです。
「人間を戦争というくびきから解き放つことはできるのか?」 これが私の選んだテーマです。
ナショナリズムに縁のない私のような人間から見れば、戦争の問題を解決する外的な枠組みを整えるのは易しいように思えてしまいます。すべての国家が一致協力して、一つの機関を造りあげればよいのです。この期間に国家間の問題についての立法と司法の権限を与え、国際的な紛争が生じたときには、この機関に解決をゆだねるのです。
ところが、ここですぐに最初の壁に突き当たります。裁判というものは人間が創りあげたものです。とすれば、周囲のものからもろもろの影響や圧力を受けざるを得ません。何かの決定を下しても、その決定を実際に押し通す力が備わっていなければ、法以外のものから大きな影響を受けてしまうのです。私たちは忘れないようにしなければなりません。法と権利と権力とは分かち難く結びついているのです!司法機関には権力が必要なのです。権力――高く掲げる理想に敬意を払うように強いる力――それを手に入れなければ、司法機関は自らの役割を果たせません。司法機関というものは社会や共同体の名で判決を下しながら、正義を理想的な形で実現しようとしているのですぅ。共同体に見直がなければ、その正義を実現できるはずがないのです。
けれども現状では、このような国際的な機関を設立するのは困難です。判決に絶対的な権威があり、自らの毛体を力尽くで押し通せる国際的な機関、その実現はまだまだおぼつかないものです。
そうだとしても、ここで一つのことが確認できます。国際的な平和を実現しようとすれば、各国が主権の一部を完全に放棄しt、自らの活動に一定の枠をはめなければならない。
され、数世紀ものあいだ、国際平和を実現するために、数多くの人が真剣な努力を傾けてきました。しかし、その真摯な努力にもかかわらず、いまだに平和が訪れていません。とすれば、こう考えざるを得ません。
人間の心自体に問題があるのだ。人間の心のなかに、平和への努力に抗う種々の力が働いているのだ。