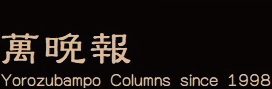移民国家、日本
明治時代の人口推計によると、1873年(明治6年)の日本の人口は3340万人だった。 江戸時代が終わった 明治維新 (1868年)から100年後の1967年(昭和42年)には、日本の人口はついに1億人をこえた。日本の人口は100年間で約3倍になった。一方で、北海道を含む海外への移住熱も高かった。北海道200万人、海外75万人、旧満州155万人。300万人以上の日本人が海を渡った歴史を持つ。
日本の移民の始まりは、1868年にハワイへの集団移住が開始されたことにさかのぼる。1886年(明治19)、日布渡航条約(「布哇国政府ト締結セル渡航条約」)が締結され、ハワイ移民が本格化した。条約に基づく移民は、計26回行われ、約3万人が渡航した。現在でもハワイの日系人の人口は30万人で、全体の4分の1を占める。
明治2年、北海道開拓使が出来ると今度は北海道が新天地となり、村ごと移住が始まる。明治から大正期にかけて約200万人が移住した。当初は奥州列藩同盟の伊達藩など主君を失った士族による移民が多かった。北の守りを司る屯田兵制度が誕生キリスト教など宗教団体や会社組織による移民も増えていった。
アメリカへの移民は、1887年(明治20)6月に福沢諭吉門下の井上角五郎が米国のシエラネバダに土地を購入して広島県人30余人を連れて入植したことや、1889年(明治22)に荒井達爾が熊本県人50人を連れて米国ワシントン州に入植したことがあるが、いずれも失敗している。アメリカは賃金が格段に高く、1887年(明治20)以降、出稼ぎ目的での渡航が激増し、1890年(明治23)在留邦人は2千人を越え、1895年(明治28)6千人、1899年(明治32)には3万5千人に達した。榎本武揚は、外相辞任後の1893年(明治26)2月、自らの理想を実現するため殖民協会を設立し、メキシコに植民地(いわゆる榎本植民地)建設を計画した。日墨拓殖会社を設立し、土地を年賦で購入し、明治30年3月には34人が渡航した。しかし、この計画は資金不足のために挫折した。
1908年6月サントス港へ到着した笠戸丸の781人を第一陣として,ブラジルヘの移住者は陸続と続き,その数は1941年までに約19万人に達した。明治以降第二次大戦による中断までの間の邦人移住者の総数は,当時の満州への移住を除いても77万人を超えた。地域別に見ると,北米地域(ハワイを含む)約37万人,中南米地域約24万人,東南アジアその他が約16万人となっている。敗戦時に旧満洲にいた日本人は約155万人といわれる。うち開拓移民は25万人。
戦後の移民は海外移住事業団が外務省の外郭団体として設立され、再び移民熱が高まる。ブラジルなど南米を中心に行われ、約25万人が渡航している。その他、研修生名目でカリフォルニアに短期間、青年を送り出していた時期もある。ちなみに海外移住事業団は現在の国際協力事業団の前身である。(萬晩報主宰 伴武澄)