人間往来29 阿片王、里見甫
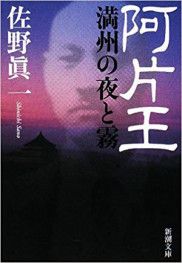
里見甫(さとみ・はじめ 1896‐1965)上海の東亜同文書院を卒業、天津日報の記者を皮切りに、満州誕生後に奉天に移り、国策通信社満州通信社の初代社長となり、陸軍と結託し、アヘン取引に関わり、阿片王と呼ばれた。
1896年、秋田県能代に生まれる。父は退役軍人で日本の無医村を回る貧しい医師だった。福岡で修悠館中学を卒業後、玄洋社の推薦で上海の東亜同文書院に入学。卒業後、1916年、青島の貿易商社、新利洋行に入社するも、3年後に倒産。いったん日本に引き上げるが、1921年、天津の邦字紙、京津日日新聞の記者となる。
約15年にわたる取材活動で蒋介石ら中国要人や関東軍の高級参謀の知遇を得る。第一次奉直戦争では東三省独立を宣言した張作霖に直撃インタビュー。軍事顧問だった本庄繁(後に関東軍司令官)の知遇を得た。1923年の津浦線の乗客数百人が土匪に襲われた臨城事件では臨城市に一番乗りして評判を高めた。
その後、北京新聞に移り、1928年、北京に入城した蒋介石との会見記事によってその名を内外に高めた。済南事件では、日本軍は国民党の内情に通じていた里見に調停斡旋を依頼し、協定調印の道筋をつけた。
この大仕事の後、里見は満鉄南京事務所に転職、蒋介石による南京政府や共産党主導の武漢政府からの情報収集に努めた。この功績が関東軍に認められ、満州における通信社「国通」の設立工作に参画。満州でのメディア乱立を防止する目的で電通と満蒙通信社が一体となったのは1932年で、里見がその代表者となった。国通は日本における後の国策通信社「同盟」発足の足掛かりとなった。
里見の国通代表は長くはなかった。次に関東軍が里見に期待したのは阿片の取引だった。 中国における阿片は蒋介石を含め政権を維持する重要な「資源」でもあった。関東軍がその「資源」を見逃すはずはなかった。熱河省は良質な阿片を産する地で、熱河省侵攻作戦も張学良の資金源を奪取する目的があったとされる。関東軍はさらに阿片の産地であった内蒙古もその勢力範囲とした。問題は天津や上海など大消費地との流通だった。
里見が本格的に阿片と関わるようになったのは1937年に起きた第二次上海事変だった。特務機関から資金調達のための阿片の販売依頼があり、ペルシャから大量に密輸された阿片の販売に着手した。青幇、紅幇につながる盛文頤なる人物を仲介者として大量に販売するルートが見出された。「阿片王」の筆者、佐野真一によれば「裏社会に人脈のある里見にしかできない仕事だった」。
里見は上海に宏済善堂という名の拠点を設け、ペルシャ阿片に引き続き、熱河阿片、内蒙古阿片の総元受けとなった。宏済善堂はもともと岸田吟香がヘボン伝来の目薬「精錡水」を中国で販売した善楽堂上海支店だった。「阿片王」には、阿片販売で得た利益について「半分は蒋介石、4分の1は南京政府の汪精衛が取って、残りの4分の1の八分を軍部に収めて、あとの2分を里見が経費を含めて取っている」という記述もあり、興味深い。阿片のお蔭で財政赤字だった南京市は「たちまち好転した」ともいわれている。
戦後、帰国した里見は極東軍事裁判でA級戦犯として巣鴨に収容されたが、なぜか無罪放免となった。(萬晩報主宰 伴武澄)
