|
|
武蔵『兵法三十五箇条』と同調する女子柔道家の感覚
2004年06月04日(金)
萬晩報通信員 成田 好三
|
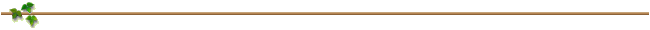
2000年シドニー五輪・柔道女子52キロ級銀メダリスト、楢崎教子氏(旧姓・菅原、文教大専任講師)が5月7日付毎日新聞運動面のコラム欄「金曜カフェ」に寄せた文章「すべての感覚動員し相手を読む」を読んで、不思議な感覚にとらえられた。楢崎氏はこの短い文章で、格闘技の競技者(アスリート)として体得した特異な感覚を、後進や真の柔道愛好家のために語っている。
それまでに楢崎氏の文章を読んだことはなかったのだが、「この文章は、以前どこかで読んだことがある」という『既視感』――この場合は『既読感』と言った方がいいか――を覚えたのである。
しばらくたって、『既視感』あるいは『既読感』の理由がわかった。楢崎氏の文章は、およそ360年も前に剣豪、宮本武蔵が書いた『兵法三十五箇条』(以下『三十五箇条』)の一節と、ほとんど同一の内容だった。いや、武蔵の書いた一節を、具体例を示しながら書いたような文章だった。
楢崎氏はシドニー五輪での銀メダルのほか、1996年アトランタ五輪で銅メダル、1999年英国・バーミンガム世界柔道で金メダルを獲得した。超一流の柔道家であり、競技者であった。菅原氏はシドニー五輪後に現役を引退した。
楢崎氏の文章について語る前に、武蔵の『三十五箇条』に触れておく。『三十五箇条』は武蔵が1641年に書いた、自らの剣術とその背後にある、体のさばきかた、感覚、思想を端的にまとめた短い覚書のようなものである。武蔵はその4年後、1645年に、五輪書を書き終えて没した。62歳だった。
『三十五箇条』は、同じく武蔵が書いた『五輪書』の下書き程度にしか評価されていない。しかし、この文章こそ武蔵が独創的に編み出した剣術と、その背景となる思想を生(き)のままに表している。『五輪書』はむしろ、武蔵の思想を一般化するために、水で薄めたようなものである。
『三十五箇条』の一節に「目付の事」と題した次の文章がある。
目を付ると云う所、昔は色々在ることなれ共、今伝る処の目付は、大体顔に付るなり。目の治め様は、常の目よりもすこし細き様にして、うらやかに見る也。目の玉を不動、敵合近く共、いか程も、遠く見る目也。其目にて見れば、敵のわざは不及申、左右両脇迄も見ゆる也。観見二ツの見様、観の目つよく、見の目よはく見るべし。若又敵に知らすると云う目在り。意は目に付、心は不付物也。能々吟味有べし。(『兵法三十五箇条』(岩波文庫「五輪書」・渡辺一郎校注より)
どこを探しても現代語訳が見つからないので、筆者が訳することにする。大意は以下の通りである。
目の向け方(治め方)は、昔はいろいろ試してみたが、今思うところはこうである。目は大体相手の顔に向ける。普段より少し細めるようにして、うららかに見るものである。目玉は動かさず、敵が近くても遠くても、遠くを見るようにする。そのように見れば、敵の技はもちろん、左右両脇まで見渡せる。(前段)
ものの見方には「観」「見」の二つがある。「観」の目は強く、「見」の目は弱くするべきである。(中段)
また敵に分からせる目というものがある。意思は目に生じるものであり、ものに現れるものではない。よくよく修練するべきである。(後段)
武蔵は、文字通り真剣でもって命のやりとりをする戦いの場で、敵をうららかに見ろと語っている。この一言だけでも、武蔵の剣術の特異さ、あるいは独創性を表していると言えるだろう。
ここからは、楢崎氏と武蔵の文章を比較してみる。楢崎氏は毎日新聞に寄せた文章の冒頭でこう述べている、
「格闘技の目の使い方は特殊で、相手と至近距離で組み合っているが、決して相手をにらみつけているわけではない。頭からつま先まで相手の全体が見えるようにしながら、双手(もろて)刈りのような奇襲技をかけてきても対応できるようにしている」
この部分は武蔵の「目付の事」の前段部分に対応している。試合中の楢崎氏もまた、視線(焦点)を一点に合わせるのではなく、相手の全体を見渡しながら戦っていたのである。人の目は、文字を読むときのように、一点に集中すると周囲が見えなくなる。そうした使い方とは逆の目の使い方を、格闘技の世界ではしていると、楢崎氏は指摘している。
この後、楢崎氏はバーミンガム世界柔道の決勝戦で体験した特異な感覚について語っている。決勝の相手はベルデシア選手(キューバ)である。2人は長い間、ライバル関係にあった。アトランタ五輪で銅メダルを分け合い、バーミンガム世界柔道では僅差で楢崎氏が勝利した。シドニー五輪決勝では、今度はやはり僅差でベルデシア選手が楢崎氏を下した。
世界柔道決勝戦での感覚を、楢崎氏はこう書いている。
「この日のベルデシア戦では、(会場に)大きなスクリーンがあり、私は彼女を見ながら彼女の背後にある映像も同時に捉(とら)えていた。本来なら、彼女だけを見ているはずなのだが、何とも不思議な感覚だった」
この部分は、「目付の事」の中段部分にあたる。武蔵の「見」の目とは、一般的な目の使い方である。「観」の目とは、どこか一点に焦点をあてるのではなく、対象物全体を見る目のことである。この試合中に楢崎氏は、実際にベルデシア選手と戦っている自分と、それを見ているもう一人の自分を意識していたのではないか。こう考えると、先の楢崎氏の文章は、武蔵の「観」「見」の目の使い方を具体的に示した文章だといえる。
楢崎氏の文章は、「いかに相手には自分の情報を与えず、自分だけ相手の情報を得るかが重要になってくる」という言葉で終わっている。これは、武蔵の後段の文章「敵に分からせる目というものがある。――」と同調した言葉と言えるだろう。
楢崎氏が武蔵の文章を盗作したなどと言うつもりはまったくない。恐らく、楢崎氏は武蔵の文章など読んでいないだろう。
柔道、剣道など現代武道は、明治期以前の古武道とは大きく離れた存在になってしまった。なかでも、東京五輪以来、五輪の公式競技となった柔道は、明治期以前の柔術(体術)とはまったく違う方向を選択した。国際競技スポーツとして、実質的にポイント制を採用するなど、欧州で発生した近代スポーツとの同化の道をたどっている。
武蔵の時代の武術家とはまったく違う世界に生きる現代の柔道家が、武蔵が晩年に到達したものとほとんど同じ感覚(境地)を獲得していたことに、驚きと、すこし大げさに言えば、楢崎氏への畏敬の念を感じてこのコラムを書いている。
楢崎氏も、試合中いつでもこうした感覚を体験したわけではないだろう。長年のライバルとの、ほとんど極限状況での試合中だからこそ体得した。
現代の柔道家である楢崎氏が体得した感覚は、西洋化した現在の社会ではほとんど顧みられることのないものである。しかし、こうした特異ではあるが独自の感覚からこそ、新しい技術やスタイル、そして思想が生まれるのではないだろうか。(2004年5月29日記)
成田さんにメールは mailto:narita@mito.ne.jp
スポーツコラム・オフサイド http://www.mito.ne.jp/~narita/
トップへ |
(C) 1998-2003 HAB Research & Brothers and/or its suppliers.
All rights
reserved.
|

