|
|
“We bomb, they suffer” “They bomb, we suffer”(1)
2004年03月20日(土)
ロンドン在住 藤澤みどり
|
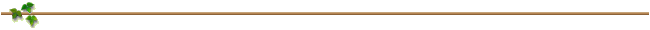
去年の3月の終わり頃だったろうか、イギリスの若い新聞記者がバグダッドにいた。イラク人にとって、その時のかれはまぎれもなく敵方の人間だったが、どうしたことか、会う人会う人みな親切にしてくれる。露骨な憎しみをぶつける人間など皆無だった。かれはひとりの男に聞いてみた。「わたしはあなたの国を攻撃している国から来た。いま、あなたの国の人々を殺している兵士と同じ国から来た。なのに、どうしてわたしに親切にするのだ」と。そう問われて男は答えた。
「あなたもわたしと同じだ。独裁者に支配された国の人間だ。この戦争はあなたの意志ではない。わたしも他の人間もそれを知っている」
尋ねた記者はたぶん、ほっとするとともに、言いようのない気まずさを感じたのではないか。そして自分に言い聞かせたかもしれない。「そうだ、わたしはこの攻撃に反対だった」と。
そう、わたしたちは反対したのだ。この戦争はわたしたちの意志ではないと反対したのだ。できることはなんでもやってみた。寝る間も惜しんで、眠れなくて。
3月20日、独裁者たちは攻撃開始を指示した。徹底した空爆で出鼻をくじき、敵の戦意を喪失させる「衝撃と畏怖」作戦。この作戦の立案にあたって、広島への原爆投下作戦が参考となっていることを知ったとき、怒りでからだが硬直した。攻撃開始時にはこの作戦は実行されなかったらしいが、テレビで見る、手加減しているはずの空爆でさえ、それはそれは恐ろしいものだった。爆弾の下にいる人々のことを想像するたびに無力感で泣けてきた。
* * * * *
その子の名前は忘れてしまったが顔は覚えている。美しい女の子、たぶん10歳とかそのぐらいの年で、バグダッド近郊の寒村に家族と暮らしていた。首都への空爆は続いていたが、何の標的もない彼女の村は、ときおり上空を爆撃機が通り過ぎるほかは攻撃前と変わらなかった。緊張感はあったが、貧しくも平穏な日常が続いていた。
ある日、空から何か落ちてきた。目撃者の話によれば、それはゆっくりと漂うように落ちてきたかと思うと空中のまだ高いところで突然爆発し、あたり一面に小さな爆弾をまき散らした。そのひとつが窓を破って家の中に飛び込んできたとき、その女の子はひとりで食事のあとかたづけをしていた。叫び声を聞いた彼女の叔母が隣室から駆けつけると、彼女は自分の流した大量の血の中に倒れていた。彼女のほかにも数人の子どもと大人が命を落とした。
明らかな誤爆による、ひょっとしたら、村の上空を通過する爆撃機がうっかり落としたクラスター爆弾による「不随意的被害」。
この記事はイラク戦の最中に新聞1ページ分を使って掲載された。その日までの村人たちと彼女の日常が細かに描写され、それが一発の爆弾によってどのように破壊されたかが淡々と報告されていた。書いたのは女性記者で、記事には死んだ姉の写真をカメラに向けて持つ妹の写真が大きく使われていた。姉によく似た美しい少女だった。戦場取材につきもののむごたらしい写真は1枚もなかったが、悲惨はじゅうぶんに伝わった。ともすれば暴発しそうになる自分の怒りや悲しみを抑えて書かれた記事だとわかった。
けがをした村人たちは病院に運ばれたが死者はそのまま村に葬られたので、女の子の死も村人の死も、この記者がここに来るまで村人以外は知らなかったろう。その記者は、誰にも気にとめられることのなかった、ありふれた戦時の死を記事にして発表することで、ほかの無数の死とは別の、ただひとつのものにした。
こういった、それぞれにただひとつの記録が、連日様々な新聞に掲載された。おのおのの新聞の方針とひとりひとりの報告者の個性によって、英国兵の側から見たりイラク人の側から見たり、怒ったり煽ったり嘆いたり、それはもう千差万別だったが、そこには当局の発表ではない生きた声があった。
ともかく覚えておこう、かれらのために他に何もできないのでせめて知ろうと、被害を伝える記事はむさぼるように読んだが、イラク戦のあいだ、わたしがもっともたくさん読んだのはインディペンデント紙だった。右派の新聞はもちろんだったが、左派と思われていた新聞までが開戦と同時に「我らの兵士をサポートしよう」に加わるか反戦色をトーンダウンさせるなかで、インディペンデントだけがきわだっていた。
インディペンデントは創刊時に、政府にも野党にも肩入れせず、右にも左にも偏らずに独立した報道を目指すとうたっていたが、メジャーな報道機関のほとんどが愛国路線に傾いたとき、もっともラディカルな新聞になっていた。「独立する」とは、なにものにも寄りかからないとは、あるいは、とりもなおさずラディカルになることなのかもしれない。
* * * * *
ベイルート在住の中東特派員ロバート・フィスクほかインディペンデントの多くの記者が地上から、爆弾の下から記事を送り続けた。フィスクの記事がなかったら、わたしのイラク戦への理解はずいぶんと違ったものになっていただろう。攻撃直後のバグダッドから送られたフィスクの記事には、かれの原稿から拾った一文がタイトルとして付けられていた。
We bomb, they suffer
われわれが爆弾を落とし、かれらが傷つく
攻撃側に自覚を強いる一文だった。
そう、これは「わたしたちの攻撃」なのだ。反対したのに独裁者が勝手に始めてしまったからと言って、わたしたちはけっして被害者にはなれない。フィスクは「We」のひとりとして「They」の中にいた。わたしたちは攻撃する側だ。出陣した英米軍だけでなく「有志連合」に名を連ねた日本の人にとっても、これは「わたしたちの攻撃」だった。傍観者ではあり得なかったのだ。
イラク戦のあいだに「わたしたちは加害者だ」と報じた日本の新聞が一紙でもあっただろうか。傷つき死んだ人たちのことを「わたしたちの攻撃で苦しんでいる」と伝えたテレビがあっただろうか。たとえイラク人とともに爆弾の下にいても、被害者にはもちろん、厳密に言えば中立にさえなれないことを伝える人は自覚していただろうか。それを受け取った人たち、テレビを見て涙を流した人たちは知っていただろうか。意に反して攻撃側に立ち、それでもなお被害者に同情を寄せる居心地の悪さと苦痛を、わたしたちは自覚的に引き受けるべきだったのではないか。
わたしの視線はフィスクとともに血まみれの病院の廊下を歩き、ミサイルに破壊された市場をさまよい、黒こげのイラク兵や市民の死体の群れを見た。どれもこれも、わたしたちのしわざだった。
* * * * *
翌年3月11日、ヨーロッパを大陸史上もっとも惨いテロ攻撃が襲った。ラッシュアワーのマドリードの3つの駅で合計10個の爆弾が爆発し、200人余が死んだ。
They bomb, we suffer
かれらが爆弾を仕掛け、われわれが傷つく
スペイン政府はテロの直後から、この犯行がバスク独立を目指す過激派組織ETA(エッタ)の犯行だと断定したが、スペインの多くの市民はそれを信じなかったようだ。金曜日に行われた追悼の沈黙デモの時に、ひとりの女性が白い大判の紙に短い文をタイプして掲げていた。新聞によればその内容はこうだ。
"They killed them because they were Spanish. I'm Spanish too."
きっとこの女性はイラク攻撃に反対していただろう。殺された人の多くもそうだっただろう。攻撃前の世論調査によればスペイン人の80%から90%が反対していたのだから。人々は政府の気持ちを変えさせようと街頭に出て激しいデモを繰り広げた。だれも「かれら」を殺したり傷つけたりしたくなかったのだ。それでも「わたしたち」は「かれら」に憎まれた。それでも「わたしたち」は「かれら」に殺された。
それは「わたしたち」が「かれら」を殺したからだ。「わたしたち」が「かれら」の国や文明を破壊したからだ。「わたしたち」が「かれら」の自尊心をずたずたにしたからだ。「かれら」は「わたしたち」に反撃し、彼女は自分もまた反撃される側の一員であることを知っている。
* * * * *
先月、空港に向かうタクシーの中で運転手とイスラムのことが話題になった。わたしはバルセロナに向かうところで、運転手はスペインで見るべきところの名前を何カ所もあげて説明してくれたのだが、それがイスラム文化の影響を受けた場所ばかりだったので「イスラム教徒なの?」とわたしは聞いてみた。他国のことであっても、それらの遺産はきっとイスラムの誇りなのだろうと思って。「そうだ」とかれは答え、パキスタンからの移民であることをあかした。「あなたもイスラム教徒なのか?」と聞かれて「違います。特に何も信仰していません」とわたしは答えた。それから「でも宗教を持っている人のことは、おおむね尊敬しています。それが平和なものであれば」と付け加えた。
しばらく沈黙があって、かれは話し始めた。「わたしはジハードには反対だ。イスラムは平和な宗教だ。殺すことを奨励するなんて、そんなとんでもない教えはない」。それから続けて日常生活に浸透するイスラムのことを話し、パキスタンのムシャラフ大統領のことを話し(ムシャラフはとてもクレバーな男だという点でわたしたちの意見は一致した)、興奮して暑くなったのか窓を開けたり閉めたりしていたが最後にこう言った。「イスラムを誤解しないで欲しいんだ」
テロは憎むべきもの、許されざる犯罪であることは言うまでもない。列車を爆破した「かれら」が、自分たちをその代表であると信じている人々にとっても、それは同様だ。かれらは「かれら」が悪事を働くたびに苦しんでいる。ブリティッシュ・パスポートを所持するイスラム教徒にとって、それはたぶん二重の苦しみだ。
あの運転手はいま何を考えているだろう。子どもたちにどう説明しているだろう。
* * * * *
列車テロの第一報を伝える翌朝の新聞で、インディペンデントは第一面全面を使って1枚の写真を掲載した。紙名と小さな広告以外は、斜め上からの俯瞰で撮影された1枚の写真だけがあった。
縦長の画面の左側を、太い蛍光ラインのついた黄色い上着を着たひとりの男が歩いている。救急隊員か事故調査係か警官か、ともかくそういった職種の人だろう。かれは左手の人差し指を伸ばして何かをカウントしながら歩いている。かれが数えているもの、それは画面の右半分に手前から奧までずらりと並んだ黒い死体袋の列だ。硬直したようにまっすぐなもの、くの字にまがった小さめのもの、中央が妙に盛り上がった
もの、様々な形の黒い袋はいまその中に横たわる人々の、その瞬間の驚きと苦しみを想像させずにはおかない。この写真の中で息をしているのは黄色い上着の男だけだ。
なぜ、こんなことに。
他の新聞が無惨に破壊された列車の写真を一面に掲載している中で、この写真だけが沈黙していた。巨大な破壊を目の前にして怒りに駆られ、声高に犯人を罵るよりも、沈黙し、なぜ、こんなことになったのかを考えなければならないのではないか。いつものように通勤列車に乗った人たちが、なぜ死体袋に入って横たわることになったのか、その理由を考えなければならない。そうしなければ、わたしたちはもうひとつのアフガン攻撃を許し、もうひとつのイラク攻撃を止められないことになる。(続)
藤澤さんにメールは mailto:midori@dircon.co.uk
トップへ |
(C) 1998-2003 HAB Research & Brothers and/or its suppliers.
All rights
reserved.
|

