|
|
「自己解体を繰り返すことに恥じない」
−協力社会にこそ新たな価値を見い出す学びの社会を(1)
2003年11月12日(水)
長野県南佐久郡南相木村診療所長 色平哲郎
|
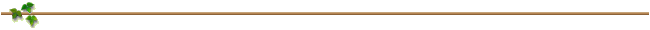
われわれはどこかで「変わらなければならない」という感覚を持っているのではないだろうか。
たとえ無自覚であったとしても、現状への“とまどい”の表れがそれを象徴している。
私たちには、見えないものを見定める力、声になっていないものを聴き届ける力、そうした能力が求められているのかもしれない。
そのためには、この社会の「構造」を自覚し、「ちがいとまちがい」をこそ大切にしながら、長持ちする人間関係のありようを学んでいくほかはないのではないか。
ムラの診療所長として、また長野県の福祉行政、教育行政のブレーンとして馳駆(ちく)の労をいとわない色平哲郎医師の視野にある日本の進むべき方向性とは--。
■「支配の構造」を自覚しなければならない
冷戦という一つの「構造」が終焉(しゅうえん)を迎えたときから市場経済への完全な移行とともに世界が単一のマーケットになるという新たな「構造」が生まれました。
そして、「こういう社会では競争が必然だ」とかけ声がかかるようにもなりました。
そのため、これまでに見られなかった変化が日本にも表れてとまどっているという現状があります。
このことは、途上国ではすでに以前から起こっていたことなのです。
しかし、日本人は自分たちの国を先進国だと考え、「みんなが中流になれてよかった」とさえ思っていました。
いま、やっと競争社会の現実が見えるようになってきたのだという気がします。
とはいえ、本来考えていかなければならないことは、みんなが感じているその“とまどい”がどこからくるのか、ということです。
それは「支配の構造」に原因があります。
われわれは、それを自覚しなければなりません。
善し悪しは別として、支配する側とされる側があるのだということを。
それは「お金」という形を通した間接的なものであったとしても、厳然と存在します。
日本の中だけにいれば、いかにも民主主義的に運営されているように感じられますが、一歩国際社会に出れば必ずしもそうではないのです。
まだソ連が存在している間は、アメリカもそうしたことをオープンには語れませんでした。
しかし、「大米帝国」がだれの目にも明らかになったいま、「支配の構造」をよく見ておいたほうがいいと思います。
決してわれわれの敵ではないけれど、われわれ自身がその構造物の中に閉じ込められもがいていることも含めて、その構造物はどのような目的で建てられ、あるいはどのような意図で改築されてきたのかを見据えていく必要があります。
それが、たとえ一種の諦(あきら)めの境地になる可能性があったとしてもです。
この日本という国では、どれほど“とまどい”があったとしても生きていけなくなることはありません。
客船でいえば三等船室に封じ込められているわけではないのですから。
ほとんどの国民が中産階級化した日本人は、いってみれば一等船室に閉じ込められた状態でしょう。
ところが同じ船内には、一等船室の他(ほか)にも、自分の荷物置き場をやっと確保できる二等船室や、座席のない三等船室、あるいは広い空間と高級な調度品を備えた特等船室の乗客もいます。
機関室やレストランの厨房(ちゅうぼう)で仕事をしている人もいます。
そうしたことを、かつての日本は、アジアの一国として肌身に感じてわかっていたはずなのですが、自分の船室のレベルが上がってくるうちに「自分らの船室以外のところは関係ない」
「国境の外は関係ない」と思うようになってきました。
しかし、その時代もすでに終わってしまったと私は思うのです。
もちろん、一等船室の中にも「二等船室へ行ったほうがいいのでは?」とか「まったく別の特殊な船室へ行ったほうがいいですよ」と言われる人がいます。
障害者など差別を受けている人たちです。
同じ船に乗り合わせている人間として、その人たちのことも考えてあげねばならない。
自分もまた身体障害者になる可能性があるのだということを認めなければならない。
そうした、「先進国に似つかわしくない人たちには別の船室へ行ってもらいましょうよね」と、
みんなが同じであることに安心を感じてウス笑いを浮かべているようでは、「構造」を感じることなど到底できないでしょう。
■声なき声を伝えられるピラミッドであるか
スペインの哲学者オルテガ・イ・ガセットが『大衆の反逆』(一九三〇年発刊)という著書の中で「大衆は、少数のエリートによる支配を乗り越えてくる存在であるけれども、彼らはみんなが同じであることをまったく恥じ入る感覚がないばかりでなく、むしろそれによって存在感を示そうという人たちである」と述べています。
少数のエリート支配が終わる時代状況を指摘したのですが、われわれは決してエリート社会に戻りたいと願っているわけではないと思います。
しかし、みんなが同じであることを前提に社会を取り仕切って安心のウス笑いを浮かべていると、「構造」が見えてこないばかりか、学校でいじめが起こっても「人と違わないことが得だ」と思うようになる危険性もあります。
それは不幸なことです。
また、先生が「正解をもっているのは私ですよ」と知識を注入するような教育を続けるのであれば、これもまた「構造」に対する気づきを奪ってしまうことにもなりかねません。
教師のほうも、そうした権力的な関係を当たり前だと思うときには、自分もまた同じような権力構造の最底辺にいる場合が多いのですが、そうした上から下への一方的な伝達に無批判な行動をとっていると、自分がどこに位置して、どういう状況にあるのかを外から見つめなおす視座を得ることがほとんどできなくなってしまいます。
学校関係者の前で、こんな話をしたことがあります。「子どもたちがノビノビ、イキイキ、ハキハキ、ニコニコ、ドキドキするような教室づくりができたらいいですよね。
その子どもたちを教え導いているのは、やはりノビノビ、イキイキ、ハキハキ、ニコニコ、ドキドキしている先生方ですよね。
そして、その先生方を支えているのは、ノビノビ、イキイキすることが大事だと考えて学校経営をやられている校長先生ですよね。
教育委員会もそれをうながすような組織ですよね」と。
そう話した後、「では、病院では、どうして患者さんや家族の方はビクビク、オドオドしているのでしょうか?」と投げかけます。
そして、「こう考えられませんか?」と言います。
「患者さんや家族の方がビクビク、オドオドしているのは、そうさせられているからではないでしょうか。
つまり、医者がノビノビ、イキイキしすぎているからなのではないでしょうか」と。
そして最後に、「自己を家畜化させられ、飼われることに慣れてしまった自分に気づいていない教員たちもまた……」と言い添えて、「彼らにこそ、”奴隷解放宣言”が必要となろうか」と結べば、聴衆の方々は絶句です。
文部科学省が作り上げた小さなピラミッドの末端に置かれている教師たちが、同じような三角形を下に作ってしまう。
それは、病院や診療所の医者にも、特養施設の所長にも、役職にある役人にも当てはまることです。
下の人たちを導き促す立場にある専門職であるけれども、それがために「専門的に善き道筋に導くのだ」という罠(わな)に陥ってしまう危険性があるのです。
しかも、下の人たちはオドオド、ビクビクはしないとしても常に依存的な、ある意味で「仕方のないこと」と感じがちな一方的なサービスにさらされることになります。
このような人たちは、そうした三角形の頂点に立つ人、あるいは中間にいる看護婦さんや寮母さんやヘルパーさんに対して言い返すことができないために、
その人たちが心の中で思っている声にならない声は沈黙の中に置かれてしまいます。
それが当たり前となれば、組織は硬直化していきます。
知的障害者の施設へ行くと、言葉のおぼつかない青年が私に対して「実は」という本心を訴えてきます。
ところが、ドアの外から足音が聞こえてくるとパッと声を止める。
知的障害があっても自分の身の安全保障に関しては考えているわけですから。
そこで私のような外部の人間がアドボカシー(代弁者)として「アラオカシー(あら、おかしい)」と感じたことを小さな三角形のトップにうまく伝えることができれば、現在のように規制緩和などの大波が押し寄せている時代にあっても、その小さな三角形でのサービスが他とは差異が際立ち、生き残れる組織にもなっていくのです。
声なき声を集約して上に伝えて襟(えり)を正していくことは、小さな三角形にとって決して損なことではなく、得な、生き残りの施策にもなるという、そういう時代であろうと思います。
一方で、その小さな三角形がたくさんあるその上にも三角形がいくつも乗っていて、教育界や医療界でいえば、たくさんの三角形の頂点に文部科学省や厚生労働省が乗っている日本の中央集権という構造のあり方に気づかなければ、次の一歩は踏み出せません。
そうした「構造」に気がつけば、自己を家畜化してしまうような文部科学省からの統制に対しても「当たり前だ」と思うことが教師としてのあるべき姿だと感じざるをえないようなつらい状況にあったのかもしれないと、たとえ同情的にでも指摘できることは第一歩なのです。
なぜなら、「そんなことはない」という反発する心の中にこそ、自らの気づきがあるわけですから。(つづく)
トップへ |
(C) 1998-2003 HAB Research & Brothers and/or its suppliers.
All rights
reserved.
|

